
建築家 ジン・ヨハネスの『フューチャー・フルーツ・ファーム』
3. Cafe Magazine
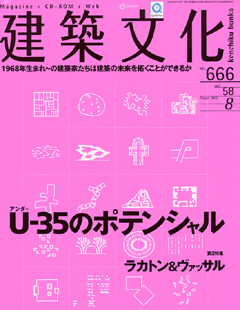
過去10年間の海外滞在作品を通して。総括ジン・ヨハネス
ブルックリン・フリーメーソンの泪
通常フリーメーソンには、血も泪もない、か?だがここで述べることはまぎれもない。最近引っ掛かっている事柄の多くは、私がしばらく日本から離れた'90年代の6年間をロンドンのAAで過ごした時のイギリス起点のヨーロッパの視点と、テロ後の2002年から今年にかけて過ごしていたニューヨークのブルックリン・スタジオでの視点の自己対立構造での試行にほかならない。ひとつの難題はヨーロッパとアメリカの相違を自分なりに理解するのがテーマだったのに加え、アメリカの最近の「古いヨーロッパ」との亀裂の地政学的シフトが単に政治外交の問題でなく、関係しているあらゆる層の個人レベルで整理しないといけない問題になった。それにしてもイギリスだけがアメリカとこうも癒着している理由は、そもそも彼らはヨーロッパ人ではないから。ユーロに不参加だし、「ユーロスターでヨーロッパヘ行こう」と言うぐらいだ。つまりイギリスはヨーロッパじゃない。またアングロサクソンの純血思想の民族意識も、両国を結び付ける要因としてはドイツ、フランスと比べ大きい。アメリカ系スコティッシュ・メーソンというのもある。ところで都市開発でのニューヨークの歴史としては、イギリスとオランダがブルックリンを競い合って開拓したのがこのエリアの始まりで錯乱の錯乱だ。つまり、『錯乱のニューヨーク』を書いたダッチの視点が、もはやイギリスとの対立構図で、ここニューヨークでは錯乱してしまっている。だから単にアメリカとヨーロッパという切り口にならず、その意味でも錯乱してハイアーグラウンド(高い地平)となっているのだ。現在のブルックリン・ハイツには歴史的建築群のプレモダンからニューヨーク・アールデコまで、いや実はアーリー・アメリカン17世紀様式までが現存する。そんなのヨーロッパにはなかったし私には不可解な陳腐で希薄(ライト・コンストラクション)な様式だった。ブルックリン内陸のブラウン・ストーン様式もしかり、そこはマンハッタンの開発以前のエリアということだ。植民地開拓時代のヨーロッパからの流れと断絶を、建築石工装飾(メーソン)の様式をくまなく検証することで、読みとく鍵にならないかと時間があればよく散策をしていた。手荒くぶっちぎって言うと、ネオコン・メーソン(ニューヨークを含む東部エスタブリッシュメント)とただの生っ粋のコンサバ・メーソン(ロンドン)の両アングロサクソン・メーソンの相違は何か。まず起源であるイギリス側から検証すると、エジプト・メソポタミア略奪博物館メーソンであると言える。それに対し他のヨーロッパ・メーソンで注目したい分類は、ギリシャ・イタリア・アフリカ北部の地中海性タートル・メーソン、フレンチ・ブルバード・ハイパーパターンのナポレオン・メーソン、ハプスブルク・スネーク・メーソン、そして共産党系リバティー・メーソンなどがあげられる。これらが、アメリカ用に改造対応される構図と思いきや、実は新たな根源的問題として奴隷制がクオリティー下げの汚点となる。メーソンと関係した職人以下の奴隷制をつくってしまったのがアメリカの内部構造の歪みの根源だ。つまり、メーソンの話してんのになんで奴隷なんかの話になっちまうんだというのが理性のレベルより現実のレベルで蔓延している社会システムを構築してしまった。もしかしたら彼らも分かって決断してたと。そこまで考えて私はいつものように高速でハイツを走り抜け、網膜におびただしいメーソニック・ディテールを焼きつける機械的な日常からふと立ち止まり、雨が石の装飾に滴るのをじっと眺めた。アジアのスタバでは「メーソンの三角形に目のロゴ」から雫が落ちてスタバのマグカップに滴る壁のイラストがあったのをこの日のニューヨークでも思い出した。コーヒーのドリップの雫とが錯綜したものは、私の心の中で滴る泪だと思い、それは飲み干すべきだった。今年初めての流氷がイーストリバーのブルックリン・ハイツ脇に辿り着いていた日のことだ。
Between Bridges (スコアの転調)
ブルックリン・ハイツの都市デザインコンペでHonor Award(名誉賞1等)をとって、ブルックリンで実際に創作活動のために移り住んだのだけれど、コンペ応募当時に相当サイトを読み込んでいたので初めて来た街という以上のものがあった。つまり国際コンペの応募時点では直接サイトは視ていなかったのだけど、CD-ROMで写真や図面、ブルックリンの成り立ちに関する歴史的コンテクストをできる限り検討していた結果、仮想とも現実とも言えない世界ができていた。『都市の仮面』というコンペタイトルが示すように、イーストリバー対岸のロウアー・マンハッタンから視てそれとサイトの持つ歩行者デッキとハイウェイからなる「地形的な断層」から、『都市の仮面』である。それは主催者側のブリーフィングとしての必然性があったし、よく言ったと思った。一方背後に広がるオレンジやクランベリーやパイナップルといった意表をついてほのぼのするストリート名が、実際植民地時代の当時の裕福なヨーロッパからの移民の日常を今でも垣間見せている。このリニアーなサイト(ブルックリン・ハイツ・プロムナード)に直交するこれらの軸線が、実用的にも記号的にも隣接関係をどう位置付けていくかがプロジェクトの重要なウェイトを占めていた。この意味で単に私の案が軽やかなスキンである以上の効果を、都市との対比として引き出したかった。そして歩行者デッキの拡張と倉庫跡地のパブリックスペースの開発プログラムに対して、最終案では歩行者デッキ、ブリッジ、『都市の仮面』としてのスキンと、直交するストリート同士が実用的にも「相互の生成起点」をつくり出し、身体的スケールで立面性(エレベーティング)に融合させている。その融合の際に用いたコンセプトをさらに「スコアの転調」とし、全エレベーションの関連におけるノーテーション(表記法)をスケールを変えながら突き詰めていった。転調を意味するBetween Bridgesはコンペ後にニューヨークで借りた自分のスタジオの下にあるぼろぼろのアイリッシュパブの名であるが、実際それは、その辺一体のDUMBOエリアを指している。ブルックリン・ブリッジとマンハッタン・ブリッジに囲まれたかつての倉庫ビル街を、今はアーティスト・イン・レジデンス/AIRとして使用しているエリアだ。私はそこで週末には黒人の同居人とブルースやジャズのジャムセッションでキーボードを演奏しながらキーを確かめながらニューヨーク・ジャズの「転調」を密かに修得していた。そしてよく晴れた午後には決まって2つの橋を渡ってマンハッタンへ行き両岸の都市的スケールの成り立ちを、体にがつんとくるハイパーな都市を体感しながら、SOHOやロウアー・イーストのマテリアル・ショップやカースト・アイアン(イギリス)様式のカフェへ行くのだ。Between Bridgesのスタジオ・プロジェクトは、そのような実生活と実際の都市の断層がハイツからシフトしてブリッジと立体交差している辺り(コンペの地図上の最左端)に位置している。2つの橋が生み出す100年持続したニューヨーク・ハイパーなスケールと鋼鉄のピン・ジョイントのスーパー・ディテールまでが、そのどこか中間でヒューマンな部分を残して歴史的な様式の段差に西陽が差し込んで演出している。
歴史の圧縮性について
ニューヨークで住み慣れてくると新しい知人もでき、そういう時には建築観についてかなり根本的なところを確認することになる。知る人ぞ知るニューヨーク在住のハゲの爺さんはいつも意表をついて突き上げてくる。この爺さんは若い頃アメリカに来た時に、モダニズムの巨匠は健在でその事務所にも入ったことがあるのだが、その後のポストモダンに関しても、実際にチャールズ・ジェンクスにも精通しているし翻訳までしている。いけてる御年配の日本人建築家なら誰でも個人的な付合いもそれぞれあってこの辺までは話のネタも尽きないだろうが、この爺さんが最近さらにいけてる理由は巨大なコルビュジエ眼鏡で、コロンビア大学の一連のデジタルな有機形態プロセスに精通してしまっていることだ。歴史的括りで私はこれを「デコン以降」と呼んでいる。ちょっと待てよ、この爺さんが視てきたことがすべて本物のリアルタイムなアメリカ建築史上の出来事であるのも凄いことだが、たかだか人の人生60年や80年で、建築史は何度ひっくり返ったのだろう。別に爺さんがひっくり返ってンじゃなくて、一生に歴史が少なくとも3度ひっくり返るのはいいことか? 途上国で革命が起きてるんじゃないんだから、あまりひっくり返り過ぎるのも野蛮で、未熟であって、クールさが足りない。日本のロボット産業や電気自動車がテクノロジーの分野としてアメリカにおいてもハリウッドのSFの時代スパンをスタティックに押し縮めているのに対し、それよりも冷静さや客観性が足りない。やはりヨーロッパにあるアメリカもともとの時代精神や様式の流れが推移する中で物事をとらえ、現代をやる方が効果もあるし可能性が膨らんできているように私には思える。メトロポリタン美術館のヨーロッパ・メーソン庭園の繋ぎさえ粗雑で、プログラミングの突合せまでもできてない。フォスターやヌーヴェルに2階部分に透明なブリッジをやってもらえ。コンペがいい。
テクノロジーの希薄化/続編
以前私はテクノロジーの希薄化としてマシンの風化などのある種の幻想を抱いていたが、その後ロンドン・ハイテクはハイテクではないなどの議論からもっと考えるようになったのだが、もちろん携帯電話の微細な電子テクノ基板や電波少年の電波増進プロセスで起こる不可視の媒体のマッピング技術、さらに発展すると、ネットワーク成立後のAAケンブリッジのゴードン・パスクの心理集合の変遷までを、テクノロジーの領域とすることも可能である。が、ロンドン・ハイテクの場合、カスティングなどのテクニーク(手工芸技術)であってテクノロジー(科学技術)ではないと言える。だからもともととやかく議論することもない。それよりも、ロンドン・ハイテクのルーツを探る上で、バッキー・フラーとの接点をどう解釈するかの方があまり語られていないし、難題だ。特にバッキーの遺作でフォールダブル(折畳み)テンセグリティーの実用化と、一連のハイテクを比較してみても、どっちが新しくて希薄化かどうかは論点の設定からして微妙である。ロン・へロンが私に教えていたレス・ザン・テンセグリティーは今でも意表をついて質的にも斬新と言えるだろう。それは彼の数少ない実作イマジネーション・ビルの膜構造とアンブレラ・ジョイントと私のクマモト・キヲスクそのものを今なお指している。
経済活動の衰退から何をどうシフトするのか
経済活動の衰退というのもある種、(社会活動の)希薄化である。日本は10年近く慣れ親しんできたので問題は気にならなくなりつつあるが、ともすると欧米に波及効果があるために、今世紀いっぱい惑星規模で感染し長引くことも覚悟の上だ。そこで注目したいのは株価のメカニズムだ。最近特に日本の若手の銀行関連の人たちもひょっとして分かっていないんじゃないかという危機感があるので明言したい。そのせいで建築界の若手に滞りがでるのは御免だ。それは今私が言うような「批評性」そのものだ。実質的な、文化的価値観や意義といった話だ。これらが次の時代にそのまま金銭に変わりうると明言したいところだが、実際は「連動」するが正解だ。つまりマーケットの日々の売り買いの要因に、政府の介入があろうと国際情勢に連動しようと、常にマーケットには事の真相の読み(リーディング)が存在する。表向きの政策がどうであろうと、時には逆の真意を「見極める」システムがすでに構築されている。「現実」とはこのメカニズムの積み重ねである。だから分かりやすい例では、新聞記者の「批評性」のレベルが問題となるし、日本が世界的に強い技術関連でも単なる新製品アップではない、仮にロボットならそれを文化的にどう使うかといったリアルな価値のレベルで震撼させた「全米握手とダンスツアー」後のマーケットの「批評性」の「見極め」となる。これは慎重な話である。実際アルソップやニールなどの建築家が「ソーシャル・コインシデンス/社会的因果と建築」について語ったのをどこかのレクチュアで記憶しているし、ごくごく日常の問題提起である。が、これがもはやきってもきれない関係として現代秩序はそうした密度や複合性を持ってしまっている。 ゆくゆくはマーケットとは違うかたちでこれらの批評性の質を測れる、まったく別のシステムでも評価可能な何かに移行すべきだ。建築や文化的側面においても。漠然と水瓶座の時代で精神性が重要だと言うだけでは生きていけない。そのためにはニュースを視たり読んだりするリアルタイムで双方向の意志決定の力が、次はどうなるかを鋭く見極め当てていく各自批評性レベルのアップと速度が必要だろう。
空間の神秘体験/ヴェローナ・イタリア編
経済活動の衰退と精神世界ヘのシフトは密接だ。ここでは私の建築プロジェクトにかかわった例を検証する。実はニューヨークで受賞後、ニューヨークに住む前に同じインスティテュートの主催したセミナーコンペでイタリア・ヴェローナに招待され、2001年の夏の1カ月を過ごした。サイトはヴェローナ郊外の石窟場で、そこにデジタル・ストーン・ミュージアムを提案するものだった。地元の行政を巻き込んでいて、ゆくゆくはゲーリーやボッタに投げたいらしい。われわれのセミナーのスポンサーはイタリア庭園脇のフレスコ画で覆われた特別スタジオを提供してくれたり、ヴェローナならではの特別な迷宮体験ができた。イタリア庭園だけでもラビリンスのような効果があったのだが、サイトのレジーナ・ストーンの石窟場を観て凄かったのが、巨大で冷たい時間感覚や、イタリア・ルネサンス様式感覚を超えた大空間だった。まさに迷い込むオーガニックな感覚である。現代のカラー大理石オブジェ埋め込み加工工場の特殊技術などを見学した後で、デジタルカメラに写った写真の中に白い浮遊するものが幾つもかさなったものが数枚撮れた。その白いエレメントは私にとってはセミナーのプレゼ案の空間構成の解法のようにも解釈できたが、根本的に神秘的な被写体である。そもそも石の持つパワーというのは数千数万年単位を経て存在している物質なので、石窟の穴の持つ神秘性と幾何学性が同調すれば、ひとたび迷い込んだ霊は、簡単に千年ぐらいを行き来するだけのパワーをその磁場に持つと理解する。それらが無数に私の写真に浮遊し、コンタクトをとってきたかのようだ。特別悪い印象はなく、むしろ協力的で千年を飛び越える山の多神教的感覚だった。
コミュニティーとユニオンの汚物、あるいはスカトロジーとエリクシール(媚薬)
神秘主義にも歴史的コンテクストがある。少数部族ならまだしも中世ヨーロッパにである。そのひとつはスカトロジーといって、鳩の糞などを利用したまじないの一種、あるいは生活法や仲間との合図に使用された。自分の朝一番の飲尿が臓器異常を回復させるというエリクシール(媚薬)もスカトロジーの神秘主義の実用例で、近代科学的ではないが、それ以前からあったヨーロッパの「知の体系で封印された部分」と言うべきだろう。日本語で数年前に出版もされたが、実はユングがニューヨークで刊行にあたって責任監修している。私が推測するに、ロウアー・イーストかヴィレッジ辺りのヒッピー・コミュニティーで部分的に盛り上がったのだろう。この辺りの建築様式は5、6層の煉瓦造というローマ時代の牢獄が実はそうであったように、アメリカ奴隷様式を鑑賞するにはうってつけのタイポロジーとなっているのも興味の湧くところだ。ところで、昔ヴィレッジのヒッピーがコミュニティーをつくったように、黒人や、最近ではゲイがそうするのは理解できるが、私がスタジオを借りたDUMBOにアーティストまでがコミュニティーをつくる意味はあるのか、と真剣に思っていた。括られるのは嫌だしもともと個人で好きにやればいいじゃん、と思った。それは住んでみて分かったのだけど、アメリカの内部事情の混乱から守る楯だ。いずれにせよ私はそれが好きじゃないし、内部が混乱したそんなコミュニティーが寄り集まって都市をつくり、州をつくり、それらがさらに統合なんて、もともとあり得ないのだ。それが体験として分かってようやく、EUの混乱にもかかわらず存在する意義というのが最近妙にしっくりいくようになった。
ケミカルな次元
神秘主義がなかなか文章などで伝えきれない問題はよくあった。でも不吉で祟られるというのもごく一部の偏った現象だ。私はあまり不吉系というのは関係していない。その証拠に実際数年前に事故をやったが、それはこれらの話よりまったく以前のことだ。つまり事故は祟りではなかった。2度の手術とリハビリの経験はある意味世間離れした、これさえ特殊体験とも言えるが、もっと信憑性のある話をすれば、手術中の麻酔による空間体験である。これは医療の開発分野だし、実用化されている合法ケミカルドラッグとも言うことができるだろう。2度目の手術は下半身麻酔だったので、手術中の記憶認識は前半途中までかなりある。その体験から言えることは、麻酔が痛みを消すというのはまったく嘘で、痛みを柔らげるというのも的確でない。私の場合は足首の外科手術だったが、はさみでちょきちょきする行為を親指のつま先の先端部に感じたのだった。手術中も体感していることをうまく言語化できないかと、ドクターにレポートしながら手術するといった変な患者だった。一言でいうと、麻酔とは痛みを局部的にシフトさせる、というコンセプトのもとで開発された、ハードドラッグである。実際にこの「痛みを局部的にシフト」という記号に触れた次の瞬間、私の脳内認識はもっとシフトできないか、という信号に切り替わり、その結果下半身だけが延長していく取り留めも収拾もつかないようなディープでアシッドな世界へ引きずり込まれてしまった。しかしそれを誘発したのもまた自分である、そのクールささえどこかに意志設定できるものなのだ。
ロンドンきゅうりの強迫観念
近年の体験的な混乱を整理するために、あるいはアメリカとイギリスのアングロの癒着に関してもっと知るために、JFK空港からロンドンに飛んだ。そこはBA専用サテライトであった。そんな政府間建築交渉は軽くやってのける、そしてテロの中でも絶対に落ちないし、落ちてはいけないアングロの強硬路線とも言える。デザイン的にもインターネット端末が自由に使えるもののただのビルで、ハイテクでもない。これだったらヨーロッパへ行く時も日本へ帰る時のように、ターミナル1からレンゾ・ピアノのパクリの大屋根でフランス人と一緒にチェックインした方が、高揚感と充実感を冷徹に楽しめるというものだ。さて、2年ぶりにロンドンへ着いて、フォスターの曲面の新市庁舎を観てハイヴィジョンで観た時とも違うリアルな空間の存在にあらためて感心し、問題点も含め現実的に見せてもらったという感じだ。シティーに建設中の曲面の高層オフィスビルの霧雨の中の青と緑の夜間照明が、ショーディッジ地区の古い路地のどこから見上げても街並みとオーバーラップし、巨大なランドマークタワーとして君臨し始めることを予感させ、ある意味脅威だ。しかしもっと変なのは、その脅威がぬめぬめした曲面の実在感覚だ。その後AAの知人に会って聞いてみると、新市庁舎に関しては構造事務所にまる投げらしいし、曲面の高層オフィスビルに関しては「今建築界はキュウカンバー(きゅうり)だわよ」ということだった。 さすがイギリスはこれさえ議論済みだから答えはシンプルなワンワード化がすでになされているのだろう。建築が2つもぬめぬめで都市的コンテクストを変えていってるのを見ると、「3本目が建つんじゃないか」というのが今のロンドンの強迫観念的なリアリティーだ。特にイギリス・コンペの読み込みには要注意だ。ストレートの斬新系じゃないと今はダメ。10年前にAAに来た時はすべてがコンサバで、100年間ずっと変わらなかったようなアンチ近代都市(コルビュジエも否定)だったのが、この数年のミレニアム景気でほとんどすべてが変わってしまった。ホプキンスやグリムショウまでがサーになった。ロジャースは政府の都市計画の総顧問に就任し、たとえばバービカン裏やパディントンの倉庫地区は「保存規制を解除」して高層オフィスのスクラップ・アンド・ビルドにGOサインを出し続けている。ウエストミンスターのジュビリー駅などはAAのチュートリアルで論じられた、日本のバブル期のリニアモーターカーの大深度地下駅のシールド工法の巨大なチューブ状のヴォイドのコンペ案の夢が色濃く反映されたものとなっている背後のコンテクストにもショックだ。これらの一連の実現案から言えることは、イギリスの合理主義的アプローチがうまく行くととてもパワフルということだ。合理主義も伝統だ(日本の伝統は畳に和紙だ)。ともするとこの分かりやすい開発のパワーというのは今後100年「もうやることがない」ぐらい社会を変えてしまったので、間違ってイギリスの権威主義的なものに今後「きゅうり」が結びつかないように注意して見ていきたい。
フード・アーキテクチャー(フレーバー・ミックス編)
イギリスのスーパーヘ行っても食のバブル・デザイン化は凄い。日本のバブル期にも人々の過剰な興味とお金の動きは食のファッション化や、食のブランド化、シェフのデザイナー化を生み出した。全米のCSで「料理の鉄人」の英語吹替え版が今でも話題らしいが、あの英語の通訳が相当難しいらしい。なぜそんなことをやっているのかまでを視聴者が理解するのは海外では困難ならしく、アメリカの一般人の無教養階層が露呈し始めているという副次的効果さえある。より日常の視点でイギリスのスーパーヘ話を戻せば、味の企画の中にフルーツ・フレーバーのイタリア・ヘルシー寄りの発想が多いが、それらを味だけで終わらせない、ミニマルなラベルデザインや、ボトルデザインまで開発できる環境に今はある。まさに「新しい企画には新しいデザインで」という西洋近代化の一貫性がここにもある。だが日本のバブルの時のように、デザイン事務所でぼこぼこ過労で倒れてんじゃないかちょっと心配にもなるぐらいの勢いも感じられる。もうちょっと息を抜いて食べ物ぐらい選びたいが、そうも言ってはいられないようだ。イタリアのスロー・フードなどにパッケージ・デザインはあり得ないが、イギリスで売り出されるEV(エクストラ・ヴァージン・)オリーブオイルは真四角なミニマルボトル詰め替え後メタリックなラベルに産まれ変わる。建築もハイテクなら食もハイテクだ。オーガニック・ヨーグルトまで各社競い合って宮内庁顔負けの渋系斬新カラーリングを組み合わせる始末だ。アングロのオーガニック遺伝子組替えの「みんなが優等生的教養派」と、スロー・フードの「ラテン理知的マフィア派」の世界対決は今後あり得る、そんな構造をロンドンに見た気がした。日本はどっちも分かると安心してはいられない。お茶のテーマである。かつてオレンジやピーチ・フレーバーの紅茶はフランスやイタリアで遊ばれたイギリスの伝統文化である。その後ロンドンのSOHOでも注文可能になった。コンサバなイギリス人もおちおちしてはいられなくなったし、実際に美味しい。そして今密かに出始めたのが、オレンジやピーチ・フレーバーの「緑茶」である。中国茶ではない、ましてやハーブなどのホワイトでもない、「緑茶」である。しかもラベルデザインの押しも強い。日本に来るのはいつかまだ分からないが、私個人的にはおちおちしたのをとっくに通り越しカウンター対策を早くも用意し始めてた。それが今回のプロジェクトの中にある「いちごフレーバー緑茶のための茶室」である。興味がある人はお茶会やるんでtelして。
バイオテクノロジーがかもしだす詩的な感覚について
有機食品や植物、花のバイオテクノロジーは微細化・希薄化するテクノロジーのもうひとつの現れである。特に日本の気候風土はこれに適しているとも言える。ディモールホセカ星咲きなどは、花弁の先端以外がくるまるために全体で見た時に星のように見える珍品種の組替えだ。ナスターチュームや時計草などの造形的でえぐいものも私はテラスで育てている。最近知ったのだが生まれた伊豆の南部では、国を含めて4つの農林試験場があるということで、バイオ研究も盛んらしい。それで子供のころから奇妙な植物に囲まれていたことになる。そしてバイオテクノロジーがかもしだす詩的な感覚について、従来のハードなテクノロジーと違って色彩や造形や幾何学的メカニズムが、生きた植物として発せられることに注目している。生息の時間サイクルやリズムとしての波動のテクノロジーであり、色彩そのものも網膜伝達系統の波動に置き変わるとも言える。そこまで言うと、BSや携帯電話の電波や電磁波テクノロジーと同種のカテゴリーに入ってくると認識することも可能だ。ただ違うのは、花は生命体であるがゆえのポエティックな情慾をも掻き立てるテクノロジーであることだろう。そしてこの特殊なテクノロジーが、建築とどう結びつく可能性があるかということが今の私の気になるテーマにもなりつつある。小さな取りかかりとしてすでにやってきたプロジェクトの中に、テラス建築というのがある。これはたとえば、私が最初にイギリスで借りたフラットがプレモダンの中層マンションみたいな様式で、ウエストボーンテラスという名が付いた建物だったし、ノッティングヒル・ゲートテラスでは実際のテラスから住空間や都市とのかかわりまでを変えていくといった「型を破りたい恐竜好きな施主」の意向を反映したプロジェクトだった。テラスというのを私が主張するというよりもむしろ切っても切れない関係になりつつあリ、ここから発展させてプロトタイプを提案するのだ。高層のコンドミニアムの可変テラスで、全面サスペンションの環境建築も可能になる。
現代建築がストイックなまでにペラペラでカスカスになっていく時に、千年程度の時代の重層感を圧縮する時間認識が見落とされてはならない。そうして初めて微細で多意義で軽めの空間操作の手法でハイパーな襞までを都市に構築可能にする。また欧米に対していつまでも牽制ができない日本は国の政策上の問題というより、個人のメーソンの思想基盤の問題である。特に古きヨーロッパとアメリカの独立を当事者意識で思想圧縮できなければ今後の現代国際ネオコン社会を牽制することは無理だ。また早すぎるターニング・ポイントの時代に何ができるのか。それは社会の一般化を拭い去り、個人のコンテクストをつくっていけばいい。個人のコンテクストがきっかけを幾らでもつくっていく時代なのだ。
(建築文化2003年8月号、全文拡大抜粋。ジン・ヨハネス、後日、建築文化によるトーク・イベントあり。)